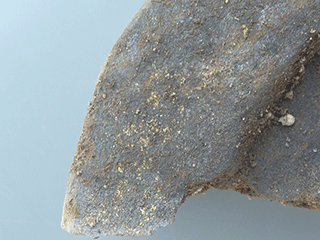4区 遺物検出状況です。

2・3層から沢山の縄文土器・石器、土偶などが見つかりました。

1区尾根上の高い所にはフラスコ状土坑と呼ばれる深さ約2m、
口径2mほどの超大型土坑が見つかっています。

4区で出土した西ノ前タイプ土偶の類似品です。
お腹やおしりの部分で、残存高さは約13cmでした。
全形とすれば、30cmを超える大型土偶と考えられます。

土偶の前後側面の写真です。
おしりや足などの表現が西ノ前の土偶とそっくりです。

2区の南側、丘陵の尾根の上から、
深鉢形土器が埋まった状態で出土しました。

先週に引き続き、3区の西側の2層の掘下げを行いました。
ここからも、たくさんの縄文中期の土器や石器が出土しました。

4区の東側にある埋没した谷部の埋土を掘り下げました。
埋土中からも、縄文中期の土器や石器がたくさん出土しました。

今週は、作業中に急激な大雨に見舞われました。
このような雨では、作業がままなりません。
雨が止むまで、現場のテントで雨宿りをします。

今週は、調査区の南東にあたる3区の遺物包含層の掘下げを行いました。

3区の南側から、10cm程度の平たい川原石を並べて囲った、
石囲い炉が検出されました。

3区で検出された土器敷石囲炉(どきじきいしかこいろ)です。
石囲いの炉の中に縄文土器片がびっしり敷き詰められた炉跡です。
こうした炉の形は、縄文中期中頃に特徴的にみられるものです。

大溝を完掘しました。写真撮影も完了。
あとは平面図に記録するだけです。

3区からは比較的に新しい陶磁器類が出土します。
「木俣牛乳店」というところの「5勺」(1合=10勺)サイズの瓶です。
高級食品だったのですね。

3区を面整理したところ、怪しい土質変化のラインを確認したので、
サブトレンチを入れて確認作業をしています。
来週も継続して掘り下げを行います。

N-1区の、金箔瓦が出土したのと同じ土坑から、
面白い模様の陶磁器が出土しました。

作業員が掘っている所が、陶磁器の出土した場所です。

N-2区からも、貴重な遺物が多数出土しているので、
出土状況の記録写真を撮っています。

柱穴の跡をタワーから撮影しました。

道路南側の調査区の表土を重機で剥いでおります。

南側の調査区も、高速道路の予定地をはさんで東西に分かれます。
これは東側の調査区です。

軒丸瓦が出土しました。
残念ながら、時期の決め手になる家紋ではなく汎用性が高い一般的な巴紋でした。

瓦が出土した遺構の完掘状況です。
大溝に平行するような細長い土坑です。
他にも遺構が重複しています。

大溝の掘り下げもいよいよ終盤です。
残念ながら、時期の決め手になるような遺物は出土しませんでした。

今週は、B-4・N-1・2・O-1区と新たに4つの調査区の遺構検出を始めました。
このN-1区は、国道112号線北側の最も東にある面積の小さな調査区ですが・・・

調査区の中央やや北より(画面左より)に、ほぼ完全な丸い形の遺物が確認できます。
大きな土坑(どこう=穴)の中にあるようです。

17世紀前半頃のものと推定される唐津焼の皿です。
縁の一部が欠けていますが、かなり良い状態で残っていました。

同じN-1区(唐津の陶器が出土したすぐ近く)から見つかった軒丸瓦の破片です。
一部(画像左下のあたり)がキラキラ光っています。
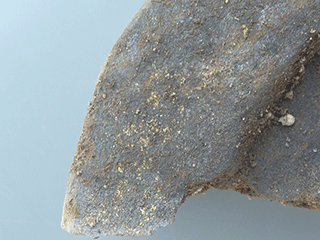
よく観察すると、瓦の表面に金が付着しているのが確認できます。
どうやら「金箔瓦(きんぱくかわら)」のようです。

いよいよ迂回路を作り、道路の下を調査する準備が整っていきます。

土坑の中の遺物も多く現われてきました。
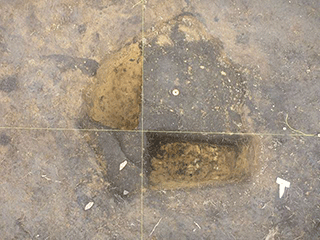
柱穴の土を対称的に掘り、柱の跡を調べます。

5区大溝の掘り下げ作業です。

大溝の最上層から、独楽(こま)が出土しました。
本体は木製ですが、軸と本体縁が金属製です。

大溝出土遺物の撮影の様子です。
使用する主力カメラも、ここ数年で中型銀塩カメラから
フルサイズデジタル一眼レフカメラへ移行しました。
Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research