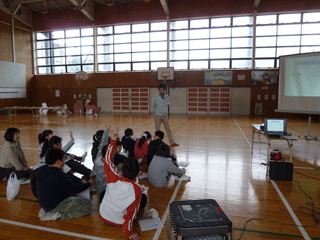不思議なかたちをした縄文時代の道具(石器)にふれながら、
どうやって使っていたのかについて、お話しを聞きました。

火きり板をおさえる人、軸をおさえる人、
弓をひいて軸をまわす人3人で、力を合わせながら火起こしをしました。
なかなか火がつきません…。
火の大切さを、身をもって学びました。

縄文人になったつもりで、えものにねらいをさだめて!

今日の出前授業で、縄文時代の生活についてのたくさんの感想をいただきました。
縄文人のくらしかたが、いまのわたしたちの生活のヒントになるかもしれません。
これからも、たくさん勉強していってくださいね。
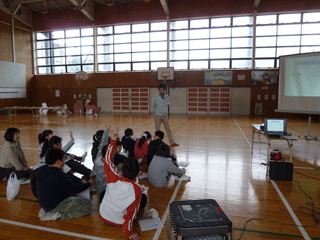
最上町富沢小学校に出前授業に行ってきました。
縄文時代の暮らしについてみんな熱心に話を聞いていました。

初めて見て、触れる土器はどんな感じでしょう。
みんなお気に入りの土器は見つかったかな?

石器で実際にものを切る体験です。
上手に石器を使いこなしていました。

弓を構えて記念撮影。
狙われる獲物の気持ちがよくわかるくらい気迫が伝わってきました。

調査員による縄文時代の話に、目を輝かせて聞き入る子供たちです。

今日の天気はあいにくの雨模様。湿度が高いとなかなか火がつきません。

縄文服を着てくるみ割りに挑戦。
中身をつぶさずにうまく割るには、それなりのコツが必要です。

自分たちの住む東根から出土した土器にびっくりです。
何に使っていたのかな?

石器で野菜切りに挑戦です。切れ味はどうでしょう。

火起こしの実演です。
みんな真剣にやり方を聞いています。

縄文人と同じやり方でクルミを割りました。
クルミの味はどうでしょうか?

はじめてみる縄文時代の石器に、みんな興味津々!
縄文時代のナイフや矢じりといった道具について、みて、さわって学びました。
石器のつくり方も学びました。

4つの方法による火起こしのしかたを体験しました。
また、縄文時代の火起こしのしかたについては、まだまだわからないことが多いことも学びました。
写真は、弓のような道具を使ったユミキリ式による火起こし。

これは、棒を手で回転させるキリモミ式による火起こし。
がんばって棒を回しましたが、この日は火がなかなかつきませんでした…。
火を起こすことがたいへんであること、火はとても大切であることを、体験しながら学びしました。

先生と一緒に弓を引き、獲物を目がけて矢を放ちました!結果は?

石のナイフ(石さじ)を使って野菜を切り、切れ味を体験。
とっても切れることに、たいへん驚きました!

本物の縄文土器を前にみんな興味津々です。
調査員の説明を真剣に聞いていました。

土器に使われている縄目を粘土に再現しているところです。
模様をつけるのもなかなか難しいことがわかったようでした。

みんな頑張って火起こしをしています。うまく火を起こせたかな?

縄文人になりきって弓矢体験!うまく弓がひけるでしょうか?

古代人の弓矢体験をしています。
狙いを定めて、フォームが決まっていますね。

縄文時代の石器を見ています。明るい所にかざすと、
きらきらひかっているところがあって、「きれいだなぁ」と感激している様子です。

みんな目がとっても真剣です。
丸い大きな石の上でくるみがうまく割れるかなぁ、
くるみっておいしいのかなぁ、いろいろ考えているところです。

自分の家から持ってきた野菜を、石器で切っています。
きゅうりやきゃべつを生でぼりぼり食べていますね。おいしそうです。

はじめに縄文時代の人々の暮らしについて説明しました。
ノートをとりながら、みんな真剣に話を聞いていました。

高畠町の遺跡から出土した土器や石器にみんな興味津々です。

火起こし体験ではみんな顔を真っ赤にしながら頑張りました。

やっとついた火に大喜びです。火をおこす大変さを感じてくれたようです。

新庄市内にある遺跡から出土した土器を見てもらいました。
持ったり、触ったり、ふだん出来ないことなので、
みんな興味津津でした。

火起こし体験の様子です。
必死にマイギリを動かしてやっと火が点きました。
大きな炎に驚いています。

みんな弓を引く姿が様になっています。
どんどん矢を飛ばして、動物パネルに当てていきます。

火起こし体験では、マイギリを上手に使う児童が多かったです。
早いグループはなんと、5分程度で火を起こすことができました。

弓矢を使って動物(パネル)を倒す体験も行いました。
全ての動物を倒すことができました。
弓を構える姿も様になっています。

石器や土器を熱心に観察しています。
授業後も、何人か質問をしに来てくれました。
Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research