
調査もいよいよ終盤です。
今週は、土層の堆積状況を図化するなど、図面の作成も進めました。

また、今週は雨に悩まされた一週間でもありました。
一日の作業の開始は、調査区内にたまった雨水の処理から始まりました。

また、雨で屋外で作業ができないときは、これまでに出土した遺物の整理も行いました。
写真は、B区から出土した鞴(ふいご)の羽口(はぐち)で、
馳上・西谷地b遺跡やその近辺で製鉄等の鍛冶が行われていたことが推測できます。

調査もいよいよ終盤です。
今週は、土層の堆積状況を図化するなど、図面の作成も進めました。

また、今週は雨に悩まされた一週間でもありました。
一日の作業の開始は、調査区内にたまった雨水の処理から始まりました。

また、雨で屋外で作業ができないときは、これまでに出土した遺物の整理も行いました。
写真は、B区から出土した鞴(ふいご)の羽口(はぐち)で、
馳上・西谷地b遺跡やその近辺で製鉄等の鍛冶が行われていたことが推測できます。

雨の日が続き、毎日排水作業から1日が始まります。

11日(日)に現地説明会を開催いたしました。
80名以上の方に調査成果をみていただきました。

遺物包含層を検出しました。
黒い土層の下の茶色い土層です。

遺物包含層から縄文時代前期の土器片が出土しました。

遺物包含層を掘るために、全長140mの足場を設置しました。

遺物包含層を掘るために、その上に乗っている土層を除去します。
泥だらけです。

ラジコンヘリでの撮影に向けて、調査区内を整えています。

今週は雨天により、作業をするには厳しい毎日が続きました。
安全に配慮しながら行っています。

清水の集落からの調査区遠景です。
中央の茶色い丘が清水西遺跡です。

E-1区の埋め戻し作業です。
土を積んだトラックが大活躍です。

E-2区の土の表面をジョレンできれいにしています。
左側に溝のような遺構が出ています。

A-3区南側で遺構を掘り下げています。
河川跡ということもあって、大きな石がごろごろ出てきます。

11月になると天気が安定せず、突然雨が降ったり、晴れになったりします。
カッパを着ての作業中に発見した虹です。
10月27日に東根市立第二中学校の文化祭で文化体験講座として
埋文センターの体験学習を行いました。

青空のもと、勾玉作りをしました。
当時勾玉がどういったことに使用されていたのかなどの説明を行いました。

実際に勾玉をつくりはじめると、みんな真剣です。
自分のこだわりを上手に出そうと、手を真っ白にしながら作りました。

火起こし体験も行いました。
さすが中学生です。あっという間に火があちこちでついていました。

今週はぐずついた天気が多く、小雨の中、足元に気をつけながら調査を行いました。
竪穴住居跡も順調に完掘していきます。
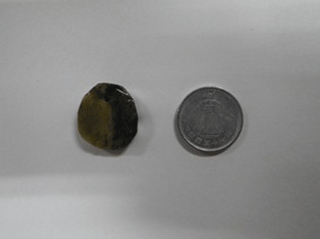
石製模造品と思われる遺物が出土しました。
上部に穴が開けられており、装飾品を模したものなのでしょうか。

11月1日、押出遺跡第5次調査が始まりました。

調査前の様子です。
中央の堀の左側(鉄の板の左側)の堀底・斜面に遺跡が位置しています。

堀底の排水を行いながら足場を作り、斜面をきれいにしています。
土器や石器が見つかっています。

今週は分析用に遺物のそばの炭化物を回収しています。

炭化物を回収して整理しています。
遺物番号を付けています。

遺物の取り上げも終わり、きれいな更地になりつつあります。

今週は、C区の完掘状況の写真撮影を行いました。
C区では、竪穴住居跡が1棟(写真手前の掘り込み)、その他、柱穴や溝状の遺構が検出できました。

また、21区の遺構の掘り下げを進めました。
21区では、柱穴と溝跡、土坑が検出され、奈良・平安時代の土器片が出土しています。