
今週は、1区と2区に分かれて調査を進めました。
1区では、井戸跡の掘り下げを行いました。
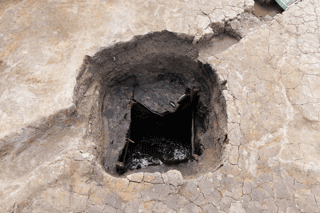
土に埋もれていた井戸枠が、はっきりと現れました。
また、井戸の底の方から、木製品が見つかりました。

2区では、河跡の掘り下げを進めました。
遺物は、土器などが見つかっています。

今週は、1区と2区に分かれて調査を進めました。
1区では、井戸跡の掘り下げを行いました。
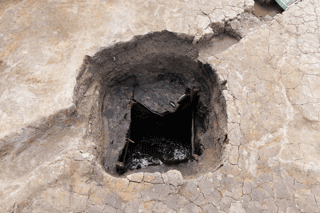
土に埋もれていた井戸枠が、はっきりと現れました。
また、井戸の底の方から、木製品が見つかりました。

2区では、河跡の掘り下げを進めました。
遺物は、土器などが見つかっています。
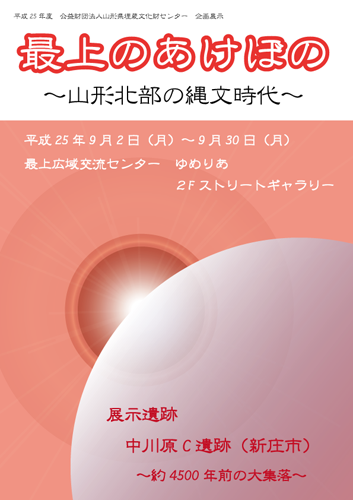
新庄市の新庄駅に併設される「ゆめりあ」にて、企画展『最上のあけぼの』を開催しています。
埋文センター初の最上地方での企画展となります。
新庄市の縄文時代の遺跡、中川原C遺跡から出土した土器や石器、
表情豊かな土偶などを展示しています。
[展示期間]
平成25年9月2日(月)~9月30日(金)
[展示時間]
5:00~24:00
[展示場所]
最上広域交流センター ゆめりあ 2F ストリートギャラリー

農道下の調査区の精査がほぼ終了しました。

直角に曲がる溝が見つかりました。
幅約2m、深さ1mほどの溝です。

溝のコーナー部分から五輪塔の火輪が出土しました。
何かの意図を持ってここに捨てられたものでしょうか。

G-1区、焼土の出土状況です。

G-1区、遺構の完掘状況全景です。

今週から新たにH-1区の調査に入りました。
調査範囲の壁を削っていきます。

SD130溝跡の掘り下げを進めています。
流木のような木や杭状の木製品が目立ちます。
杭が打ち込まれている箇所もあります。

こちらもSD130溝跡を調査しているところです。
こちらでは、杭の他に、20cm前後の川原石が広く敷きつめられています。
同じ溝跡でも、場所によって全く違う調査状況になります。

井戸跡を完掘しました。
出土した遺物から判断すると中世の井戸だと思われます。

溝跡を切る土坑から土師器の杯が密集して現れました。

接合すれば完形になると思われます。

調査区G-1南東角の遺構より石組が現れました。

調査区G-1土坑(どこう=穴)より高坏が出土しました。

竪穴住居の完掘状況です。

今週から、いよいよ2区の調査が始まります。
まず、重機での表土掘削を行いました。

週の後半には、2区の全景写真を撮影することが出来ました。
縦に長い範囲が2区になります。

全景の撮影が終わったら、いよいよ遺構の掘り下げに入ります。
1区から続いている遺構もあるようです。

週前半は雨に悩まされました。
雨の中でも草刈りなどの作業を行います。

井戸跡から石鉢が出土しました。

井戸が二つ並んで現れました。

直径2mを超える大型の土坑(SK115)です。
遺構の周縁部に、火山灰と考えられる白い土が廻っているのがみられます。
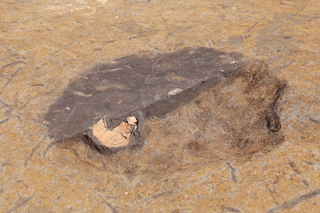
SK116土坑を半分掘ると、全体の形がわかる土師器の坏(つき)がみつかりました。
土師器は、素焼きで赤い色に焼きあがるのが特徴です。