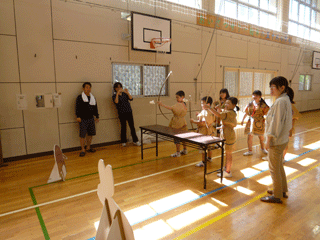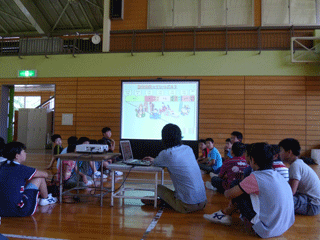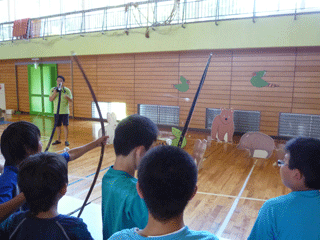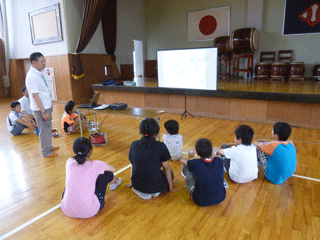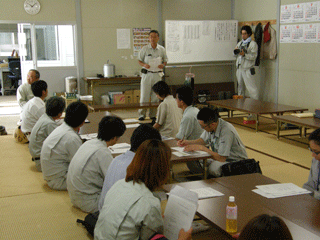6月26日、山形市内の小学校の先生方40名が研修にいらっしゃいました。
三の丸跡をふくむ山形市内の遺跡から出土した遺物にi触れて、みなさん興味津々です。

昨年度の第11次調査区跡を写真パネルで紹介しました。
意外に身近な場所に昔の人々の生活の痕跡が残っていることに気づかれたようでした。

続いて、今週調査が終了したばかりのF調査区の見学です。
立派な石組みの井戸跡を前に「おおっ!」と感嘆の声があがります。

最後に、現在調査中のG-1調査区で遺構検出作業の体験です。
「ジョレン」で薄く土を削っていくと、
溝跡や柱穴跡などの遺構が見えてくるのを実感されていました。

柱穴や溝からは様々な遺物が出土しています。
お膳として使われた折敷(おしき)が出土しました。

溝から鎌と考えらえる金属製品が出土しました。

柱穴の壁面に張り付くように瓷器系陶器のカメが出土しました。
また、柱穴の底面からは擂鉢が出土しています。
いずれも中世前期のものと考えられます。

今週もジョレンを使って遺構検出を行っています。
バックの葉山も雪が融け、夏の訪れを感じさせます。

トータルステーションという測量機器を使用し、
調査区内の遺構や遺物の地点を特定するための表示釘を打ち込んでいます。

粘土層で固いところは移植べらで掘り進んでいきます。
力のいる仕事で大変な作業です。

土層注記(土の色の調査)が終わった遺構から、
掘り残したところを掘り下げていきます。

週の後半にはゲリラ豪雨に見舞われ、調査区が水浸しになりました。

豪雨により調査区に大量の砂が流れ込んでしまったため、
調査区の復旧作業を行いました。

先週に引き続き遺構の検出を行っています。

検出した遺構に白線を引いています。

遺物も少数ですが出ています。

本物の土器と聞いてみんな大興奮!
興味津々で触ったり、匂いを嗅いだりしていました。

6人全員で力を合わせての火起こしです。
みんなで協力して火が点いたときは喜びと同時に大変さも感じたみたいです。
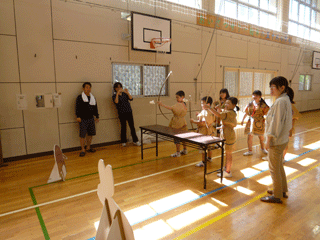
縄文服を着て気分はもう縄文人!
弓矢で獲物を狙う姿がバッチリきまっています。
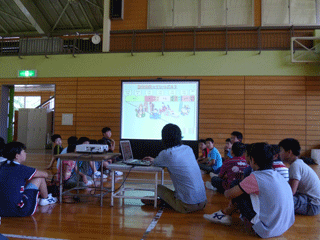
縄文時代のお勉強です。
「縄文時代はどれぐらい長い?」の質問に、様々な意見が。
答えは約1万年以上です。

火起こしでは悪戦苦闘の末、やっと火が付きました。
みんなの粘り勝ちです。
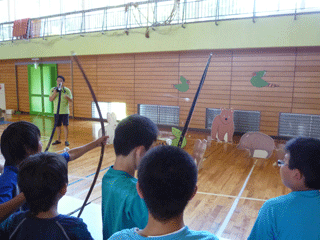
弓矢体験では、なかなか動物にあたりません。
動いている動物を狩っていた縄文人はすごいね。
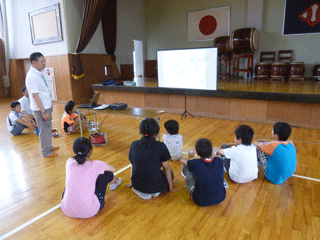
まずはスクリーンの前に集まって、縄文時代のお話を聞きます。
昔の人たちは、どんな暮らしをしていたのかな?

学校の近くの「かっぱ遺跡」から出土した遺物を見学しました。
遺跡名も変わっていますが、出土遺物も、特徴的なものが目立ちます。

火起こしでは、唯一の女子チーム。
チームワークで無事着火に成功し、富沢小の着火率は100%でした。
拍手!

高畠町の押出遺跡の整理作業を見学していただきました。
押出遺跡は漆塗りの土器や縄文クッキーなどの出土品が特徴的で、全国的にも有名な遺跡です。

最後に展示室も見ていただきました。
県内の遺跡で出土した遺物のごく一部ですが、年代順に展示してあります。
皆さん、興味深げに見て行かれました。
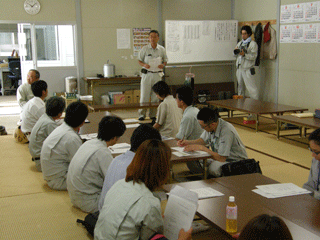
本年度2回目の文化財担当者研修会です。
座学では、会場となった蝉田遺跡・松橋遺跡の概要や出土遺物の説明に加え、
事務所や器材庫の設置方法などについても解説しました。

屋外では、試掘調査について研修しました。
確認できた遺構の図化に挑戦中です。

午後からは場所を松橋遺跡に移し、遺構検出を体験していただきました。
実際に鍬を手にして地面を削ると、溝跡や柱穴等を確認することができました。
Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research