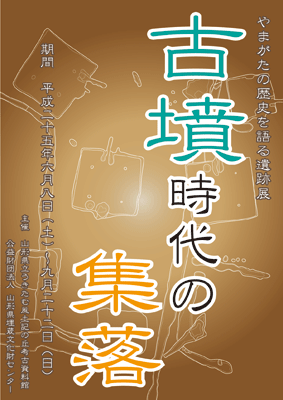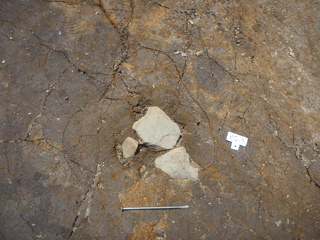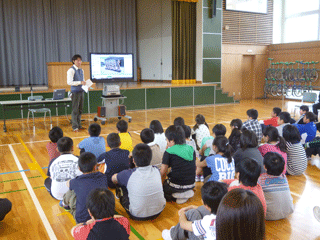山形県県立うきたむ風土記の丘考古資料館と当センターとの共催の企画展を開催します。
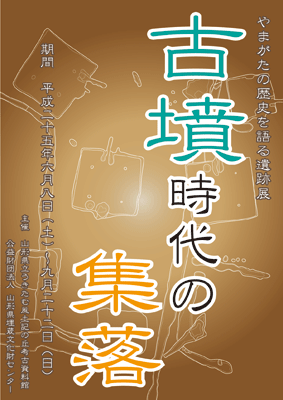
『古墳時代の集落』というテーマで、川前2遺跡(山形市)・鎌倉上遺跡(米沢市)・
矢馳A遺跡(鶴岡市)の遺物を展示します。
いずれも最近報告書が刊行されたばかりの遺跡で、
大々的な展示は初めてとなります。

集落から出土した土器などの生活用品や、
勾玉・管玉といった祭祀に関するものなど、
当時のムラでの生活の様子が伺える資料です。
【開催期間】
平成25年6月8日(土)~9月22日(日)
【休館日】
毎週月曜日、祝日、年末年始
【開館時間】
9時~17時(入館は4時30分まで)
【場所】
山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 企画展示室
東置賜郡高畠町大字安久津2117
TEL:0238‐52‐2585 (地図)

検出した遺構ひとつひとつに、「SK○○」というように遺構番号(名前)をつけ、
ラベルに書いて打ち付けていきます。

番号(名前)のついた遺構は、移植へらなどを使って、慎重に掘り下げていきます。
遺物も出てきます。

F区のほぼ中央部に大きな石を組んだ遺構が姿を現しました。
井戸跡の可能性があります。

先週に引き続き、面整理作業を進めました。
地面が乾く場合は、水を撒くこともあります。
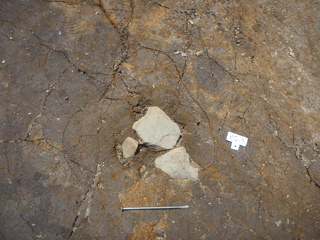
面整理によって、遺物が出土しました。
これは、砥石(といし)のようです。

今週で、1区の遺構検出作業が終わり、全景写真を撮影することができました。

今週は晴天の日が多く、作業がはかどりました。
遺構の検出作業を継続しています。

タワーの上から調査区の全景を撮影しました。

多数の柱穴や溝などが見つかっています。
来週からいよいよ遺構の掘り下げが始まります。

バックホウで表土の掘削を始めました。土を観察しつつ、
遺構が確認できる面まで慎重に掘り下げていきます。
調査区北東部分では約20cmで遺構面が確認できます。

表土掘削後、遺構面をジョレンや両刃鎌などの道具を使ってていねいに削り、
遺構の存在や形を確認していきます。
遺構には、黒い土が堆積しているようです。
遺構周辺から遺物も多数見つかり、目印として割り箸をさしています。

幅約1mの溝跡で、調査区の北から南まで延びていることが確認できました(南北60m)。
溝の中からは、杭がある程度規則的に打ち込まれた跡や、人頭大の川原石がまるで
敷き詰められたような痕跡がみられました。
ガラス瓶なども見つかっていることから、近現代の堰跡ではないでしょうか?

今週もジョレンで土を削り、遺構を探していきます。

遺構が見つかったところに白線を引いていきます。

白線を引いた遺構を、平板測量(平板という器具を使った測量)によって図化していきます。

先週から松橋遺跡の発掘が始まりました。
まずは調査区に生えている雑草を刈っていきます。

重機で掘り下げるための基準を作るため、調査区の端を線掘りしています。

重機で遺構が確認できるところまで掘り下げます。
掘立柱らしき遺構が確認できました。
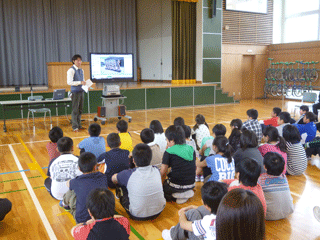
大石田北小学校では、5・6年生合同で授業を行ないました。
職員の問いかけにも積極的に答える元気な子供たちです。

火起こし体験真っ最中です。
この後、無事に火を起こすことが出来ました。

弓矢は一見簡単そうに見えるけど、矢をつがえるのも一苦労します。
みんな、ちゃんと矢を射てたかな?

遺跡から出土した土器や石器について説明を受けた後、実際に触る体験をしました。
本物を触った時はどんな感じだったかな?

今回は浜田小学校に出前授業に行ってきました。
スライドを使った説明にみんな熱心に耳を傾けていました。

本物の石器にみんな興味津々!
自分も作ってみたいと言う子もいました。
夏休みの自由研究にできるかな?

火起こし体験では、道具の使い方に一苦労!
昔の人の大変さがわかったと思います。

弓矢でうまく獲物を仕留められたときには大歓声が上がっていました。

置賜地方の代表的な遺跡「押出遺跡」の土器を持って行きました。
縄文の意味をよく理解してくれたようです。

くるみ割りは初めての子がほとんど。
今日はケーブルテレビの取材も来たので、なおさら緊張してしまいます。

どこに行っても人気なのが弓矢体験。
パネルでできた動かない的でも、なかなか当たらないので思わず夢中になってしまうようです。
Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research