県立村山特別支援学校高等部の1年生2名がセンターで職場体験を行いました。
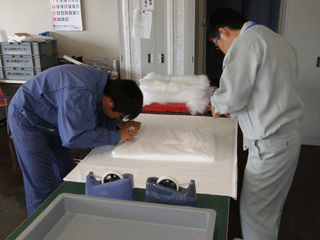
遺物を保護するための綿座布団をつくってもらいました。
段々慣れて、たくさんの座布団をつくっていただきました。

出土した遺物の洗浄作業では、一つ一つ丁寧に洗ってくれました。
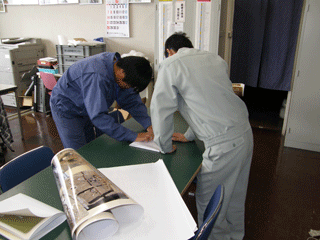
センターのイベント速報会のポスターの発送作業です。
厚い紙をきれいにおるのに一苦労です。
6日間色々な作業を真面目に頑張ってこなしてくれました。
県立村山特別支援学校高等部の1年生2名がセンターで職場体験を行いました。
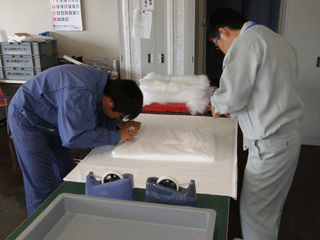
遺物を保護するための綿座布団をつくってもらいました。
段々慣れて、たくさんの座布団をつくっていただきました。

出土した遺物の洗浄作業では、一つ一つ丁寧に洗ってくれました。
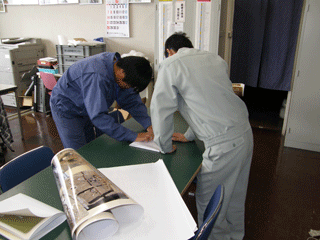
センターのイベント速報会のポスターの発送作業です。
厚い紙をきれいにおるのに一苦労です。
6日間色々な作業を真面目に頑張ってこなしてくれました。
10月13日にセンターの公開講座「バスで遺跡を見に行こう!-日本海側北限の古墳文化を探る―」が行われました。
28名の参加者と一緒に、山形市と天童市の古墳やその時代の遺跡をバスで巡りました。

山形市の菅沢(すげさわ)古墳では古墳の頂上で、
発掘調査で様々な種類の埴輪などが多数出土したことなどの説明を受けました。

山形市の大之越(だいのこし)古墳では整備された円墳を間近で見学しました。

山形市の嶋遺跡では古墳時代の集落について説明を受けました。

天童市の西沼田遺跡公園では復元された住居を見学しました。

最後に現在調査中の蔵増宮田遺跡の見学をしました。
河跡から大量の遺物や木製品が出土しています。

ベルトを掘り下げた所から大きめの石核と思われる遺物が出土しました。

中央部から写真を撮ります。
遺物を取り上げる前に位置をきちんと記録します。

タワーと呼ばれる台からの写真です。
空中撮影のためにきれいにしてあります。

21区の全景写真を撮影するため、遺構の検出作業を進めました。
遺構の多くは柱穴と溝、土坑です。

21区の遺構検出状況の全景写真です。
今後、遺構の掘り下げを行っていきます。

金曜日に調査A区の空中写真撮影を行いました。
これは西側から撮影した様子です。

土曜日には現地説明会を行い、100名ほどの方に来て頂きました。
遺物、遺構の説明を熱心に聞いてくださいました。

これまで調査してきたSG6河川跡と並行して、SG50河川跡の掘り下げも行いました。
SG6に比べ、遺物の出土は少ないようです。

SG6河川跡から見つかった遺物です。
今週も人形(ひとがた)がみつかりました(手前右側)。
縦17cmで、以前見つかった物(縦26cm)に比べると、小さいサイズです。

SG6河川跡からみつかった木製品で、ツチノコと考えられます(長さ18cm)。
ツチノコは、蓆(むしろ)などを編む時の錘(おもり)です。
中央部分を細く削り、そこに巻きつけて使用するようです。

図面作成を行っています。
規則的に配置されたと考えられる遺構の断面(遺構の掘り方・深さ)や、遺構間の間隔などの情報を図化します。

Eー1区全景、遺構を掘り下げた状況です。

Aー3区全景、表土をはぎ取った状況です。

今週からは、今年度の発掘調査では最後の調査区となる、国21区の調査を開始しました。
調査区は、米沢市道にあたるため、道路のアスファルトの除去から始めます。

アスファルト・表土の除去が終わったら、ジョレンによる面整理を行い、
遺構・遺物の確認をしていきます。

今回の調査区は、東西に細長い調査区となっています。
まだ未確定ですが、溝状の遺構と多数の柱穴らしき痕跡が確認されました。
今後、さらに面整理・遺構検出を進めていきます。

頂上の遺物が出土した範囲に立っています。
おおよそ円形になっています。

北側斜面角の深掘りをした穴です。
赤い土の下から礫層がでてきました。

南側斜面の掘り下げです、そろそろ掘り終わる予定です

調査区西側端にある川跡とみられる遺構を掘り上げました。
遺物の数としては少ないのですが、雨水が入ってしまうと土をあげるのも一苦労です。

以前紹介した「坩(かん)」が出土した地点の周りからも、古墳時代のものと思われる土器が多数出土しています。
また、27日(土)の調査説明会では見つかった遺構や出土した遺物を紹介します。