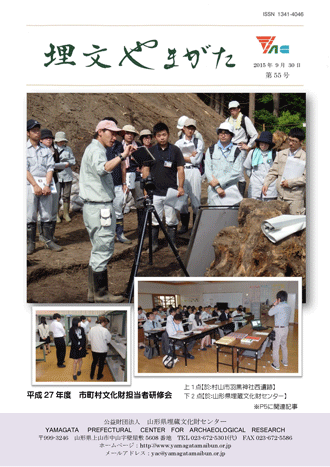今週も、3区の遺構の掘下げと記録作業を中心に、調査を行いました。

昨年度の調査で、3区の南斜面には、3層のクロボク土層の上に、地山の土が乗った「盛り土遺構」があることがわかっていました。その盛り土遺構の盛り土層を掘り下げると、多数の土器や石器が残されていることが認められました。

3区の東側では、3基の小型のフラスコ状土坑が見つかりました。腹ばいになりながら、土坑内の堆積層を掘り下げました。

10日(土)には、羽黒神社西遺跡の第2次発掘調査の現地説明会を行いました。遺跡の近所にお住いの方々を中心に、およそ40名以上の見学者が来跡されました。丘陵の尾根に深く掘られた、約4,300年前のフラスコ状土坑について、みなさんたいへん興味津々の様子でした。

2区捨て場(SF133)の遺物出土状況を平面図にしました。
写真のとおり、遺物が多く出土しています。

2区捨て場(SF133)の土層ベルトを掘り下げています。
遺物は少量ですが、出土しています。

10月31日(土)に、上竹野遺跡の第2回発掘調査説明会を行います。
弥生時代前半を中心とする、広範囲の捨て場が確認され、土偶・
土版・石棒などの祭祀に関する遺物が出土しています。

1区の竪穴住居跡

結髪土偶の出土状況
ぜひ足をお運びください。
現地説明会案内(PDF)
日時:平成27年10月31日(土) 10:00~(雨天決行)
調査遺跡:上竹野遺跡
場所:大蔵村清水字上竹野(地図)

1区の竪穴住居跡の写真撮影を行いました。
床面からも土器・石器が出土しています。

2区捨て場(SF133)の遺物出土状況を撮影しました。

4区捨て場(SF134)の遺物出土状況の撮影に備え、清掃作業を行いました。発掘作業も10月を迎え、少しずつ寒くなってきました。

4区捨て場(SF134)の掘り下げに着手し、出土状況の撮影を行いました。2区の捨て場同様、土器・石器が出土しています。

今週も3区と4区の遺構の精査と記録作業を中心に調査を行いました。これまでの調査で、3区と4区の南側に遺構が集中していることが判っています。

3区の西側の尾根上にあるフラスコ状土坑は、およそ深さが2.5mほどありました。中に炭火を入れていることや、壁の崩落と埋め立てを繰り返していることが判りました。

フラスコ状土坑の堆積状況を記録するために、図化作業を行いました。

5区の3層掘り下げでは、5区の東側に遺物が集中していたことが判りました。これらの遺物は、出土状態から、3区の南側斜面のものが5区のほうへ落ちてきた可能性が考えられます。

8区の面整理作業を行いました。北側は去年の調査区の続きです。昨年度調査した大溝の続きが出てくるでしょうか。

8区の南側の遺構検出作業です。
比較的大きな遺構が重なり合ってるようです。

8区南側の遺構検出作業が完了した状況です。近現代の新しい遺構と重なっていますが、東西方向に平行する2本の溝が検出されました。道路跡の可能性も考えられます。引き続いて8区の中央部と南側の遺構検出作業も進めています。

少し古そうな遺構から、かわらけが出土しました。手捏(てづく)ねで作られ、口縁部を撫でて整形しています。

P-2区東側の調査も残りわずかとなりました。
調査区中央の溝の調査を行い、土の堆積状況を記録します。

P-3区南側の完掘全景です。掘立柱建物や竪穴住居など多くの遺構が重なり合った密度の高い調査区でした。

M-1区では遺構の調査を終え、下層の確認を行いました。
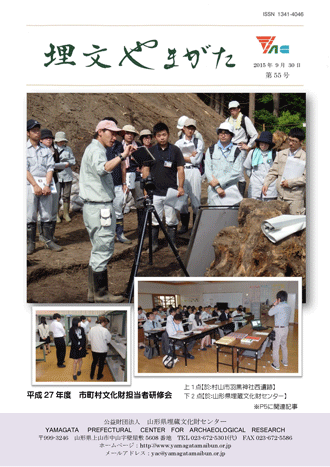
「埋文やまがた 55号」を刊行しました。
ご一読ください。

10月10日(土)に羽黒神社西遺跡第2次調査の現地説明会を行います。
調査では、縄文時代中期の遺構(遺物廃棄遺構・フラスコ状土坑・盛り土状遺構)や、遺物(縄文土器・磨製石斧・石鏃・石器)が出土し、平安時代の墓と思われる土坑が確認されました。

調査の様子

フラスコ状土坑の断面
ぜひ足をお運びください。
現地説明会案内(PDF)
日時:平成27年10月10日(土) 14:00~(雨天決行)
調査遺跡:羽黒神社西遺跡
場所:村山市名取字清水西(地図)
9月27日(日)、センター公開講座『~歴史遺産ウォーキング~行ってみっべ!掘ってみっべ!山形城ぶらり旅』が開催されました。
天候にも恵まれ、絶好のぶらり旅日和となりました。

はじめに山形市教育委員会が調査している本丸西堀跡の現場を見学させてもらいました。めったに入ることのできない堀底に足を踏み入れ、スケールの大きさに圧倒されました。

さらに当センターによる発掘調査現場や、江戸時代当時の出入口のかたちを示す道路のクランク、削られずに残った土塁の一部など、街中にひそむ三の丸の痕跡を見てまわりました。

お昼休憩を挟んで、午後は最上義光歴史館の見学からスタートです。施設ボランティアの方に義光公の人物像や長谷堂合戦などについて解説してもらいました。

今回のイベントでは、見学だけでなく三の丸跡第17次の調査現場で発掘体験も行いました。土を薄く削り、色や質の違いを観察しながら昔の人が掘って埋もれた跡を探しています。
Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research