
A区中央にある、川跡の調査に取り掛かりました。
西の川(SG1)は比較的浅く、川辺部分に沿って土器が出土しています。

隣接する東側の川(SG2)のトレンチは、かなりの深さとなりました。
川底の砂層から流木や遺物が出土しています。

土師器の甕(かめ)も、出土しました。

流木の下から、棒状の木に樹皮の紐が巻かれた木製品も出土しました。
なんの用途で使われていたものでしょうか。

最終週ということで、上空から調査区の全景を撮影しました。

三の丸10次の調査区と国史跡三の丸土塁跡(写真奥の森)を一緒に写した写真です。
10次調査区と土塁跡の間に十日町口の城門があったとされています。

最後に、堀の掘方を確認するために、石敷きをはずして地山層まで掘り下げました。
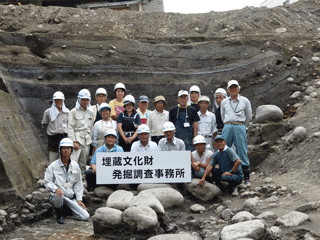
三の丸10次調査の参加者で記念撮影をしました。
みなさん、大変な調査本当にお疲れ様でした。
夏休みこどもミュージアムめぐりの企画展『ビィーちゃんの生まれた縄文時代へタイムスリップ!』を
開催中です。
より多くの方々に楽しんでもらうため、展示期間を8月22日(水)まで延長いたします。
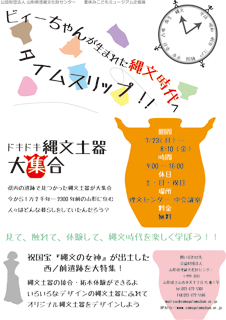
(PDF)
山形県内出土の縄文土器が大集合!
ビィーちゃんと一緒に縄文時代へLet’s Go!!


見て、触れて、体験して楽しく縄文時代が学べます。

拓本体験や土器の接合体験もできます。

オリジナル土器をデザインしてビィーちゃんシールをもらおう!

また夏休みこどもミュージアムスタンプラリーでスタンプを集めた方には
オリジナル粘土細工をプレゼント!

日時:7月23日(月)~8月22日(水) 9:00~16:00
休日:土・日・祝日
場所:山形県埋蔵文化財センター 地図
ぜひ来てください。
お待ちしています。

調査区の壁面が乾燥し、崩れるのを防ぐため、ブルーシートで養生し、
さらに土のうを壁面沿いに積み上げました。

遺構検出状況の写真を撮影しました。
調査区内で、黒色土が広がっている区域が確認できます。
この範囲からは土器片や炭化物が多数出土しています。

写真撮影後、黒色土の範囲を,土層観察用のベルトを設定し、少しずつ掘り下げました。
多数の土器片や炭化物が混じっているものの、明確なプラン(遺構の形)が見えてこないため、
今後集中的にこの遺構の精査を行います。

未加工の石刃です。
刃渡りの長さを調べるために定規を置いています。

遺構の白線も多くなりました。どんな営みが行われていたのでしょうか。

縄文時代の土器や石器です。
土器の文様から県内では数少ない早期(約6,000年前)のものと思われます。

2区の中央部付近から、いくつかの石器や土器が出土しました。

2区の地層を調べるために、壁沿いにトレンチを掘りました。
地層を調べると、2区は、ひとむかし前は田んぼであったり、湿地が広がっていたり、
洪水などで土砂が積もったりしていたと考えられます。

調査区の表面を、丁寧に薄く削ることによって、土の色や質の違いがはっきりします。
むかし掘られたあなの跡などが見えてきます。
また、土器や石器が顔を出すことがあります。

調査区南東部分の遺構検出作業を行っています。
最低でも5条以上の溝が見つかりました。
それぞれ、流路や堆積した土に違いがみられます。

溝の一部を試し掘りしました。
断面を観察すると、2条以上の溝が重なり合っていることとや、溝に堆積した土の状態、深さがわかります。

調査区(3区)の西壁南端にかかる、竪穴状遺構の断面図を作成しました。

調査区(4区)の溝跡(SD60)を先週に引き続き、ベルトをはずしたところ、土師器坏などが出土しました。

ラジコンヘリによる空中写真撮影を行うため、調査区(3・4区)の面整理を行い、当日に備えました。

ラジコンヘリによる空中写真撮影を行いました。
写真はラジコンヘリから送られてくる、画像を確認しながら、カットを決めていきます。

全員で調査区の周りの草の除草作業をしました。

三連休中の降雨により、シートで保護した遺構にも、雨水が入ってしまいました。
丁寧に遺構から水をかき出します。


今週も遺構から多くの古銭が出土しました。
まだまだ土の中には多くの古銭が眠っているのでしょうか。

まとまった雨が降ると、水捌けの悪い調査区は、あっという間に水没していまいます。
この日は、排水ポンプで水を抜いた後、土を乾かしてから作業に取り掛かりました。

今週は、調査区全体の壁の清掃から作業を行いました。
遺跡全体の土の堆積状況を確認したあと、必要な土層部分の撮影、断面図の作成を行います。

A区の中央に位置する河川跡と溝跡の調査に取り掛かりました。
まずはトレンチを設定し、どの程度の深さがあるか確認していきます。

A区とB区の間を流れる用水路に、カルガモ親子がいました。
Yamagata Prefectural Center for Archaeological Research


