
直径1m程の土坑に大きな石がたくさん投げ込まれていました。
右下の石は長方形に加工されているように見えます。

石を取り上げてみると、中世の供養塔である板碑(いたび)の破片が多数含まれていました。
少なくとも5個体の板碑が捨てられていたようです。

別の溝跡から出土した板碑です。
二条の線刻が確認できます。

直径1m程の土坑に大きな石がたくさん投げ込まれていました。
右下の石は長方形に加工されているように見えます。

石を取り上げてみると、中世の供養塔である板碑(いたび)の破片が多数含まれていました。
少なくとも5個体の板碑が捨てられていたようです。

別の溝跡から出土した板碑です。
二条の線刻が確認できます。

G-1区のほぼ中央にある竪穴住居跡の北東部からは
土師器・須恵器などの遺物が集中して出土しています。
周りには焼土(しょうど=赤く焼けた土)も確認できます。

同じ竪穴住居跡の中にある土坑(どこう=穴)からは、
須恵器の蓋(ふた)などの遺物も出土しています。
おおよそ8世紀(奈良時代)あたりのものと思われます。

G-1区北東部の土坑(どこう=穴)からは、ほぼ完全な形に近い小型の甕(かめ)など、
大量の遺物が出土しました。
この1週間は遺物の「出土ラッシュ」でした!

本格的な遺構精査に入りました。

大きな溝跡は各所にベルトを設置し、土がどのように堆積しているのかを記録します。

井戸跡と思われる大きな遺構も掘り進めています。

まだ終わっていない遺構の測量を行い、
無事遺構測量を終えることができました。

道出遺跡1次・2次調査も今週で終了となりました。
洗浄し、まとめた器材を搬出しています。

今年度発掘調査にたずさわった作業員、関係者の皆さま、
ご協力ありがとうございました。
8月9日(金)に中山地区公民館主催の体験学習会が行われました。
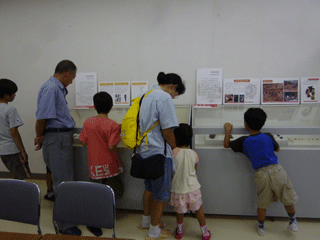
センターのお仕事を見学した後、展示室にも案内しました。
大昔の遺物に驚きの声があがっていました。

続いて体験です。
まずは火おこしに挑戦です。
暑い夏の日に汗だくになって頑張っていました。

縄文クッキーづくりです。
みんな「おいしい!」と喜んで食べていました。
8月9日に米沢興譲館高等学校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環で
センターでの講義が行われました。

センターの整理作業の様子を見学しました。
細かな仕事に感心していました。

『社会と科学~埋蔵文化財から人類の過去に迫る』と題した講義を行いました。
考古学で活用される科学技術についてセンター職員がお話ししました。


実践体験として赤外線カメラでの文字資料の観察と木製品の保存処理を学んでもらいました。
写真は出土した木製品と保存処理後の木製品に実際に触ってもらった様子です。
その感触の違いに保存処理の必要性を感じてもらえたようです。

去年に引き続き2回目となる上山城での体験講座です。
今年は去年より気温が高く、外で行なった勾玉作り体験では、
みんな汗びっしょりになりながら頑張って作っていました。

体験メニューの中でいつも大人気の弓矢飛ばし体験!
みんな暑さも忘れて狙った獲物に当てようと必死でした。

当センター職員による石器製作実演も行いました。
実際に製作している姿を見られることもあってか、みなさん足を止めて話を聞いていました。

室内ではアンギン編みも行いました。
最初のうちはぎこちない動きだったのが、徐々に慣れてきてみんな綺麗に編んでいました。
当日参加頂いたみなさん、暑い中ありがとうございました。

今週も雨に悩まされた一週間でした。
写真は、調査区北東部の水を排水している様子です。

わずかな雨の合間に、遺構を精査することが出来ました。
石製品が確認できます。

掘り下げた遺構の断面です。

Gー1区の状況です。
硯など様々な遺物が出土しています。

井戸跡の状況です。
ここまで掘り下がりました。

竪穴住居跡の調査の様子です。
十文字にセクションベルト(土層観察用の畦)を残して掘っていきます。

直径60cmほどの円形に小さな石を敷き詰めた遺構が見つかりました。
周辺に同様の遺構が3基隣接しています。

大小の石が投げ込まれたような状況で見つかりました。

上の遺構から出土した板碑(左)と方形に加工された石製品(右)です。